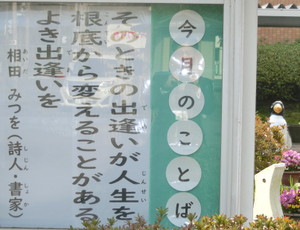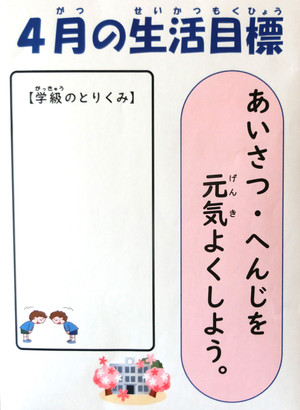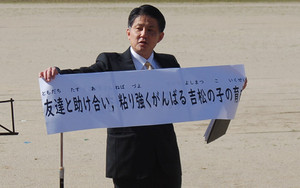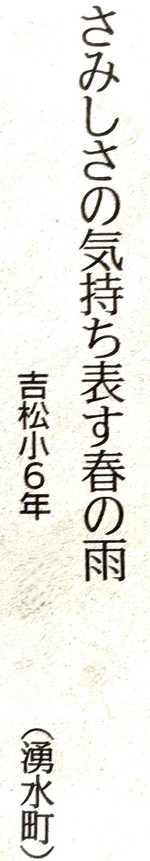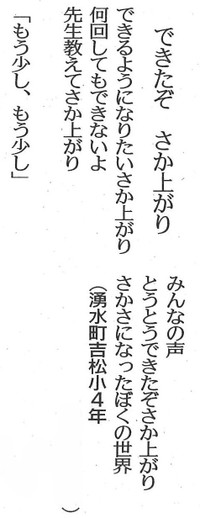4月8日(火)「今日の給食」
今年度も昨年度に引き続き,湧水町学校給食共同調理場の学校栄養士の先生から,「スクールランチカレンダー」の転載許可をいただきましたので,本ブログにアップしてまいります。ご家庭でお子さんと話題にしたり,夕食の献立を考える上での参考にしたりしていただけましたら幸いです。
【今日の献立】
①麦ごはん ②牛乳 ③じゃがいもの味噌汁 ④豚肉のしょうが炒め

【食べ物のはなし】「給食の準備や後片付けについて」
給食当番は,当番をする前に健康観察をするようにしています。具合が悪い時には当番を代わります。代わりの人もきちんと給食着を着ています。後片付けにも責任をもって最後まできちんとしています。今日の深ねぎは,湧水町内で作られた金山ねぎです。